|
20世紀末のわが国の政治的虚空(その9)
<いわゆる政権担当能力について>
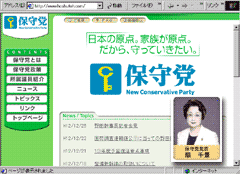  1月7日に放映されたNHKの「日曜討論」で、保守党党首の扇千景さんが、「野党は自公保連立政権打倒というけれど受け皿がないじゃないですか。私たちには、自公保という受け皿がちゃんとあります」といっていました。私は扇千景さんが自民党にいたときからよく知っています。扇さんは、自民党が野党になった平成5年にはまだ自民党にいました。党の政治改革本部の会合などで、こんな自民党ではもうダメですよというようなことをさんざんいっていました。そして、自社さ政権ができる少し前に自民党を離党していったと記憶しています。 1月7日に放映されたNHKの「日曜討論」で、保守党党首の扇千景さんが、「野党は自公保連立政権打倒というけれど受け皿がないじゃないですか。私たちには、自公保という受け皿がちゃんとあります」といっていました。私は扇千景さんが自民党にいたときからよく知っています。扇さんは、自民党が野党になった平成5年にはまだ自民党にいました。党の政治改革本部の会合などで、こんな自民党ではもうダメですよというようなことをさんざんいっていました。そして、自社さ政権ができる少し前に自民党を離党していったと記憶しています。
 この人は宝塚出身だけに演説はたいへん上手く、いろいろの会で自民党の宣伝をしていましたが、要するに自民党だけが政権担当能力がありますという類の演説をしていたような気がします。旧福田派に属し、いわゆる自民党の保守派の宣伝政治家といっていいと思います。扇さんの冒頭の言い草を聞いて、もう少し若かったころの彼女の雄姿を改めて思い出し、それと二重写しのものを感じました。人間というのは、変らないというのか進歩しないといえばよいのか、まあそういうものですなー。 この人は宝塚出身だけに演説はたいへん上手く、いろいろの会で自民党の宣伝をしていましたが、要するに自民党だけが政権担当能力がありますという類の演説をしていたような気がします。旧福田派に属し、いわゆる自民党の保守派の宣伝政治家といっていいと思います。扇さんの冒頭の言い草を聞いて、もう少し若かったころの彼女の雄姿を改めて思い出し、それと二重写しのものを感じました。人間というのは、変らないというのか進歩しないといえばよいのか、まあそういうものですなー。
 扇さんのことはいいとして、各種の世論調査などで自民党がいちばん評価されているところは、政権担当能力があるということです。自民党のいいところは、、現に政権党であるということと政権担当能力がいちばんあると見られていることといってよいと思います。しかし、多くの国民は自民党の政治を支持していません。矛盾といえば、これほどの矛盾はありません。これはもう笑えないジョークです。どうしてこんなことになるんでしょうか。 扇さんのことはいいとして、各種の世論調査などで自民党がいちばん評価されているところは、政権担当能力があるということです。自民党のいいところは、、現に政権党であるということと政権担当能力がいちばんあると見られていることといってよいと思います。しかし、多くの国民は自民党の政治を支持していません。矛盾といえば、これほどの矛盾はありません。これはもう笑えないジョークです。どうしてこんなことになるんでしょうか。
  私にいわせればこういうことです。ある程度の数のある政党ならまたどんな連立の組み合わせだって政権を担当することはできるし、いま現に政権を担当している自公保連立にも真の政権担当能力なんてないということです。現に細川連立内閣だって存続しえたし、自社さ連立政権だってけっこう長く存続しました。このことからいっても、またいわゆる革新自治体だってけっこう持ちました。日本の官僚機構はそれほど優秀だし、したたかだし、また尊大だということです。政党や政治家をちゃんと立てることをしながら、自分たちのやりたいことは少しも譲ろうともしなければ、譲りもしないということです。 私にいわせればこういうことです。ある程度の数のある政党ならまたどんな連立の組み合わせだって政権を担当することはできるし、いま現に政権を担当している自公保連立にも真の政権担当能力なんてないということです。現に細川連立内閣だって存続しえたし、自社さ連立政権だってけっこう長く存続しました。このことからいっても、またいわゆる革新自治体だってけっこう持ちました。日本の官僚機構はそれほど優秀だし、したたかだし、また尊大だということです。政党や政治家をちゃんと立てることをしながら、自分たちのやりたいことは少しも譲ろうともしなければ、譲りもしないということです。
 ある政党に政権担当能力が本当にあるかどうかは、その政党が掲げる政治的理念にしたがって官僚組織をちゃんとコントロールして実際の行政に反映させる力があるかどうかということです。そんな能力など、自民党にだって全然ないとはいいませんがごく一部で、ほとんどないといった方がいいでしょう。長年この党にいる、そして大臣をしたこともある私がいうのですから間違いありません。政策通といわれる政治家のほとんどは、課長補佐や係長が持っている知識を知っているというという程度の話であって、その官僚の論理のどこが間違っていてどう変えさせるかという能力ではないのです。政治家に求められている能力とは、そういうものだと私は思っています。 ある政党に政権担当能力が本当にあるかどうかは、その政党が掲げる政治的理念にしたがって官僚組織をちゃんとコントロールして実際の行政に反映させる力があるかどうかということです。そんな能力など、自民党にだって全然ないとはいいませんがごく一部で、ほとんどないといった方がいいでしょう。長年この党にいる、そして大臣をしたこともある私がいうのですから間違いありません。政策通といわれる政治家のほとんどは、課長補佐や係長が持っている知識を知っているというという程度の話であって、その官僚の論理のどこが間違っていてどう変えさせるかという能力ではないのです。政治家に求められている能力とは、そういうものだと私は思っています。
 いま、みんなが政治は変らなければならないといっています。国民は政治を変える力を持っています。しかし、実際の政治を変えるためには、官僚組織をちゃんとコントロールして行政のやり方をキチンと変えなければ、国民が願っている政治を変えることにはならないでしょう。そのためには、本当に優秀な能力のある政治家や政党が必要なのです。ある程度の政党は、官僚組織に対抗する知識と能力のあるシンクタンクを作るくらいのことをしなければならないと思います。 いま、みんなが政治は変らなければならないといっています。国民は政治を変える力を持っています。しかし、実際の政治を変えるためには、官僚組織をちゃんとコントロールして行政のやり方をキチンと変えなければ、国民が願っている政治を変えることにはならないでしょう。そのためには、本当に優秀な能力のある政治家や政党が必要なのです。ある程度の政党は、官僚組織に対抗する知識と能力のあるシンクタンクを作るくらいのことをしなければならないと思います。
 しかし、こんなことは一朝一夕にできることではありませんから、役職についた政治家が修羅となってやらなければならないことだと考えます。自治大臣になったとき、私は自治行政にそんなに知識があったわけではありません。それでもいくつかのことをやりました。まず、地方自治体が外国人を採用するかいなかはその地方自治体の自由にするということでした。それまでは、自治省は事実上何の法律的根拠がないのに「当然の法理」としてこれを制限していました。 しかし、こんなことは一朝一夕にできることではありませんから、役職についた政治家が修羅となってやらなければならないことだと考えます。自治大臣になったとき、私は自治行政にそんなに知識があったわけではありません。それでもいくつかのことをやりました。まず、地方自治体が外国人を採用するかいなかはその地方自治体の自由にするということでした。それまでは、自治省は事実上何の法律的根拠がないのに「当然の法理」としてこれを制限していました。
  自治省は、都道府県や大きな地方自治体に自治省の職員を出向させています。私は、そのことはいいとしても同じポストに連続して出向することを止めさせました。そうすれば、その自治体の特定のポストが自治省枠として固定することを防げると考えたからです。私がこの構想を発表したところ、同じ内閣で厚生大臣をしていた小泉純一郎氏と建設大臣をしていた亀井静香氏も、わが省もそうすると賛同してくれました。しかし、ふたを開けると実際は全然変っていませんでした。私はひとつの例外もなく実行しました。こんなことは、大臣が頑として厳命すればできるのです。 自治省は、都道府県や大きな地方自治体に自治省の職員を出向させています。私は、そのことはいいとしても同じポストに連続して出向することを止めさせました。そうすれば、その自治体の特定のポストが自治省枠として固定することを防げると考えたからです。私がこの構想を発表したところ、同じ内閣で厚生大臣をしていた小泉純一郎氏と建設大臣をしていた亀井静香氏も、わが省もそうすると賛同してくれました。しかし、ふたを開けると実際は全然変っていませんでした。私はひとつの例外もなく実行しました。こんなことは、大臣が頑として厳命すればできるのです。
 このほかにも、投票時間の延長・不在者投票の条件緩和を徹底的にやるように支持しました。その結果、現在のようになったのです。自民党からは恨まれていますが、民主主義のためには致し方ないと思っています。また、新幹線の建設に交付税措置を行い、新幹線建設費を50パーセントUPしました。これなどは、財政局長と3日間徹底的に議論して決めました。これまでにも話題になったことはあるのでしょうが、官僚の抵抗にあって決められなかったのです。 このほかにも、投票時間の延長・不在者投票の条件緩和を徹底的にやるように支持しました。その結果、現在のようになったのです。自民党からは恨まれていますが、民主主義のためには致し方ないと思っています。また、新幹線の建設に交付税措置を行い、新幹線建設費を50パーセントUPしました。これなどは、財政局長と3日間徹底的に議論して決めました。これまでにも話題になったことはあるのでしょうが、官僚の抵抗にあって決められなかったのです。
 私は自治行政にそんなに深い知識はありませんでしたが、わずか10ヶ月の在任期間でもやる気になればこのくらいのことはできるのです。大臣には、それだけの権限があるのです。ですから、政党や政治家が本気に行政を勉強して、いま国民の視点にたって改革しなければならないのは何かを真剣に考えれば、政治はいくらでも行政を変えることができるのです。そういった能力のある政党や政治家が、本当に政権担当能力のある政党であり政治家だと私は考えています。またこのようなことが実際にできるようになったとき、政治指導の政治(行政)が行われたということができるのだと考えています。 私は自治行政にそんなに深い知識はありませんでしたが、わずか10ヶ月の在任期間でもやる気になればこのくらいのことはできるのです。大臣には、それだけの権限があるのです。ですから、政党や政治家が本気に行政を勉強して、いま国民の視点にたって改革しなければならないのは何かを真剣に考えれば、政治はいくらでも行政を変えることができるのです。そういった能力のある政党や政治家が、本当に政権担当能力のある政党であり政治家だと私は考えています。またこのようなことが実際にできるようになったとき、政治指導の政治(行政)が行われたということができるのだと考えています。
 最後にもうひとつ、この際いっておきたいことがあります。それは、官僚の堕落ということです。明治以来の官僚は、「我は、国家なり」という気概と気迫をもって仕事をしてきました。日本に本当の政治家がいなかったのですから、彼らがその気概と使命感をもってこの日本の設計をしてきたのです。明治・大正の高級官僚は、官僚であるとともに政治家でもあったのです。戦後の復興をリードした高級官僚にもそのような気概と気迫がありました。私が国会にでた昭和54年のころは、まだ少しはそのようなものを感じさせる官僚がいましたが、最近ではそのような官僚は本当に少なくなってしまいました。このことは、優秀な官僚がそういうんですから、まず間違いないと思います。官僚自身も自己改革をしなければならないとこの際ハッキリといっておきます。 最後にもうひとつ、この際いっておきたいことがあります。それは、官僚の堕落ということです。明治以来の官僚は、「我は、国家なり」という気概と気迫をもって仕事をしてきました。日本に本当の政治家がいなかったのですから、彼らがその気概と使命感をもってこの日本の設計をしてきたのです。明治・大正の高級官僚は、官僚であるとともに政治家でもあったのです。戦後の復興をリードした高級官僚にもそのような気概と気迫がありました。私が国会にでた昭和54年のころは、まだ少しはそのようなものを感じさせる官僚がいましたが、最近ではそのような官僚は本当に少なくなってしまいました。このことは、優秀な官僚がそういうんですから、まず間違いないと思います。官僚自身も自己改革をしなければならないとこの際ハッキリといっておきます。
<大河の流れを見つめよう!>
 私は、信濃川をみて育ちました。いま自分が見ている河は日本一の河であるということは、私の人間形成にかなり大きな意味をもちました。いま、私たち政治家がいちばん真剣に考えなければならないことは、国民は何を考え何を求めているのだろうかということだと思います。1億2700万の日本人のものの考え方や意見は、それこそ無数にあります。しかし、それらを貫き大勢としてどこに向かっているのか、また向かうべきなのかをみる眼力がなければ、政治家ではないと思います。 私は、信濃川をみて育ちました。いま自分が見ている河は日本一の河であるということは、私の人間形成にかなり大きな意味をもちました。いま、私たち政治家がいちばん真剣に考えなければならないことは、国民は何を考え何を求めているのだろうかということだと思います。1億2700万の日本人のものの考え方や意見は、それこそ無数にあります。しかし、それらを貫き大勢としてどこに向かっているのか、また向かうべきなのかをみる眼力がなければ、政治家ではないと思います。
 すべての政治的・経済的・社会的現象を貫くいちばん基本的なコンセプトは、自由ではないでしょうか。そして、それは評価すべきことだと私は考えます。私は、自由を求める国民がアナーキーな無責任な動きをしていないと思います。自分の自由を求める国民は、他人の自由を尊重することをちゃんと心得ているとみています。このことさえシッカリしていれば、自由主義の原理でこの国を運営していくことは大丈夫なのです。多少の例外がないわけではありません。しかし、いま私たちが見なければならないのは、大勢なのです。目の前の大河の流れなのです。 すべての政治的・経済的・社会的現象を貫くいちばん基本的なコンセプトは、自由ではないでしょうか。そして、それは評価すべきことだと私は考えます。私は、自由を求める国民がアナーキーな無責任な動きをしていないと思います。自分の自由を求める国民は、他人の自由を尊重することをちゃんと心得ているとみています。このことさえシッカリしていれば、自由主義の原理でこの国を運営していくことは大丈夫なのです。多少の例外がないわけではありません。しかし、いま私たちが見なければならないのは、大勢なのです。目の前の大河の流れなのです。
 この日本を自由主義の原理で運営していくことは、いまや国民的合意━コンセンサスがあります。しかし、これをちゃんとわきまえた政党があるかというと、先にみたとおり、自民党にも民主党にも自由党にもそういう人もいれば残念ながら自由主義者とはいえない人もけっこういます。すべての問題はここにあると私は考えます。本来ならばそれぞれの党がこのことについて真剣に議論して、本当に国民の期待に添う党になったならば、その党は多くの国民の支持を得ることができるでしょう。 この日本を自由主義の原理で運営していくことは、いまや国民的合意━コンセンサスがあります。しかし、これをちゃんとわきまえた政党があるかというと、先にみたとおり、自民党にも民主党にも自由党にもそういう人もいれば残念ながら自由主義者とはいえない人もけっこういます。すべての問題はここにあると私は考えます。本来ならばそれぞれの党がこのことについて真剣に議論して、本当に国民の期待に添う党になったならば、その党は多くの国民の支持を得ることができるでしょう。
政党にはそれぞれ歴史もあり、経緯もあります。そう純粋な理論や原理だけでひとつの政党を作れるものでもありません。それはある程度やむを得ないことだとは思います。しかし、これだけ政党離れが進んでいることを、政治家は真剣に受け止めなければならないと思います。いまいちばん国民の支持を多く受けている自民党も、公明党との連立と今回の加藤騒動で自由を愛する人たちの支持を失ってしまいました。大河を貫く自由を愛する国民のからみたら、特殊な人々が作っている政党・政権になっているのだと思います。それが極端に低い内閣支持率なのだと思います。事態は、極めて深刻なのです。
 昭和45年、言論出版妨害事件であまりにも有名な 昭和45年、言論出版妨害事件であまりにも有名な 『創価学会を斬る』の中で、藤原弘達氏はこういっています。 『創価学会を斬る』の中で、藤原弘達氏はこういっています。
 「(公明党が)自民党と連立政権を組んだ時、ちょうどナチス・ヒットラーが出た時の形態と非常によく似て、自民党という政党の中にある右翼ファシズム的要素、公明党の中における狂信的要素、この両者の間に奇妙な癒着関係ができ、保守独裁を安定化する機能を果たしながら、同時にこれをファッショ的傾向にもっていく起爆剤的役割として働く可能性を非常に多く持っている。そうなった時には日本の議会政治、民主政治もまさにアウトになる。そうなってからでは遅い、ということを私は現在の段階において敢えていう。」 「(公明党が)自民党と連立政権を組んだ時、ちょうどナチス・ヒットラーが出た時の形態と非常によく似て、自民党という政党の中にある右翼ファシズム的要素、公明党の中における狂信的要素、この両者の間に奇妙な癒着関係ができ、保守独裁を安定化する機能を果たしながら、同時にこれをファッショ的傾向にもっていく起爆剤的役割として働く可能性を非常に多く持っている。そうなった時には日本の議会政治、民主政治もまさにアウトになる。そうなってからでは遅い、ということを私は現在の段階において敢えていう。」
 慧眼というのは、恐ろしいものです。いままさに自民党は公明党と連立を組んでいます。そして中曽根元首相、石原都知事、野中弘務、亀井静香などといった政治家が異常に張り切り権勢を誇っています。自民党は選挙で負けながらも、なぜか自公保連立政権は安定しています。そして、長年の懸案事項があまり本格的な議論もない中で、トコロテンのように次から次と国会を通過しています。まさに藤原氏が危惧していた事態が現に起こっています。だから、国民は自公保連立政権に強い危惧をもち、一貫して不支持の表明をしているのだと私は思います。 慧眼というのは、恐ろしいものです。いままさに自民党は公明党と連立を組んでいます。そして中曽根元首相、石原都知事、野中弘務、亀井静香などといった政治家が異常に張り切り権勢を誇っています。自民党は選挙で負けながらも、なぜか自公保連立政権は安定しています。そして、長年の懸案事項があまり本格的な議論もない中で、トコロテンのように次から次と国会を通過しています。まさに藤原氏が危惧していた事態が現に起こっています。だから、国民は自公保連立政権に強い危惧をもち、一貫して不支持の表明をしているのだと私は思います。
 しかし、政治の世界で公明党の政権参加を問題にし、批判する人はほんのわずかとなっています。マスコミも労働組合もほとんど問題にしたり、批判していません。本当は心のなかではおかしいと思いながら。なぜでしょうか。率直にいって創価学会=公明党が怖いからです。創価学会=公明党は敵対者や批判者に対して容赦ない攻撃を仕掛けています。その一方で、いろいろな懐柔策を膨大な組織と豊富な資金を使って行っています。その結果なのです。私は、ここに一種のファシズム的なものを感じ、深い危惧もっているのです。 しかし、政治の世界で公明党の政権参加を問題にし、批判する人はほんのわずかとなっています。マスコミも労働組合もほとんど問題にしたり、批判していません。本当は心のなかではおかしいと思いながら。なぜでしょうか。率直にいって創価学会=公明党が怖いからです。創価学会=公明党は敵対者や批判者に対して容赦ない攻撃を仕掛けています。その一方で、いろいろな懐柔策を膨大な組織と豊富な資金を使って行っています。その結果なのです。私は、ここに一種のファシズム的なものを感じ、深い危惧もっているのです。
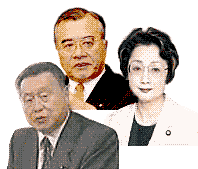  国民は自由を求めているにもかかわらず、自公保連立などという藤原氏がファッショと呼ぶものがこれに対峙しています。いま日本の政治を考えるとき、これが本質的な問題です。しかし、自由を求めるこの大河の流れを堰きとめることなどだれもできるはずがありません。このことをシッカリと認識し、果敢に行動することが、自由を愛する政治家のなすべきことです。 国民は自由を求めているにもかかわらず、自公保連立などという藤原氏がファッショと呼ぶものがこれに対峙しています。いま日本の政治を考えるとき、これが本質的な問題です。しかし、自由を求めるこの大河の流れを堰きとめることなどだれもできるはずがありません。このことをシッカリと認識し、果敢に行動することが、自由を愛する政治家のなすべきことです。
 それぞれの政党には、それぞれの歴史的経過があり、それゆえに理念的には不完全であり未完成です。自民党についていえば、リフォームによって本来の自由民主党という名にふさわしい党となることは、もう不可能なのではないかと私は考えています。加藤騒動はこのことをハッキリさせてしまいました。他党のことを私はここでいうつもりはありませんが、似たような事情がそれぞれあるように感じます。少なくともリフォームをする程度で、自由を求める国民の大多数の支持やアイデンティティーを得ることができる政党はないように思います。 それぞれの政党には、それぞれの歴史的経過があり、それゆえに理念的には不完全であり未完成です。自民党についていえば、リフォームによって本来の自由民主党という名にふさわしい党となることは、もう不可能なのではないかと私は考えています。加藤騒動はこのことをハッキリさせてしまいました。他党のことを私はここでいうつもりはありませんが、似たような事情がそれぞれあるように感じます。少なくともリフォームをする程度で、自由を求める国民の大多数の支持やアイデンティティーを得ることができる政党はないように思います。
  現在の状況は、ちょうど幕末に似ていると思います。政治家はみなそれぞれの政党や派閥に所属していますが、21世紀の政治や国民の政治意識からみたら、それはあまりにも古くなり硬直化しています。その政党や派閥を少々リフォームしたくらいでは、新しい世紀の課題に応えることもできませんし、国民の政治的意識にマッチしたものとなることはできません。明治の志士たちが、それぞれの藩を離れて日本という国を考えたとき、明治維新が始まりました。これと同じようなことを考えなければならない、それがいまの政治を閉塞状況から解き放つ唯一の道だと思います。 現在の状況は、ちょうど幕末に似ていると思います。政治家はみなそれぞれの政党や派閥に所属していますが、21世紀の政治や国民の政治意識からみたら、それはあまりにも古くなり硬直化しています。その政党や派閥を少々リフォームしたくらいでは、新しい世紀の課題に応えることもできませんし、国民の政治的意識にマッチしたものとなることはできません。明治の志士たちが、それぞれの藩を離れて日本という国を考えたとき、明治維新が始まりました。これと同じようなことを考えなければならない、それがいまの政治を閉塞状況から解き放つ唯一の道だと思います。
 自由を愛する政治家は、己を束縛している政党から自由であれ、これが21世紀初頭の政治の課題であり、ここから出発することが新しい世紀の政治をつくる唯一の道であると私は考えます。 自由を愛する政治家は、己を束縛している政党から自由であれ、これが21世紀初頭の政治の課題であり、ここから出発することが新しい世紀の政治をつくる唯一の道であると私は考えます。
(了)
11:30 東京の事務所にて 東京の事務所にて
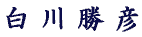
|
